
図解!2025年12月の縁日カレンダー|年末の納め拝みとは?
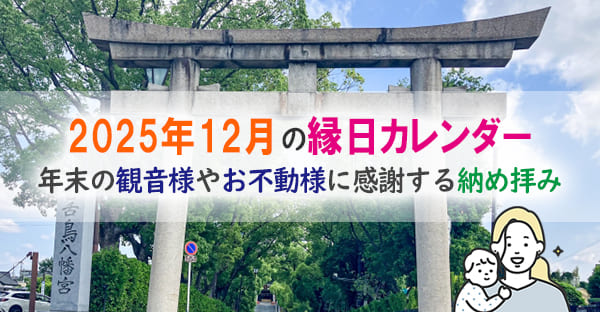
・「縁日」とはなに?お祭りとは違うの?
・12月の縁日に参拝をすると運気アップ?
・2025年12月、特定の神仏との縁日は?
「縁日」とは、特定の神仏と人々が繋がる・ご縁が深くなる特別な日です。
毎年12月に、お世話になった特定の神仏の縁日に参拝をして感謝を捧げることで、これからもお見守りいただけます。
本記事を読むことで、「縁日」とはなにか?参拝するご利益や、観音様や不動明王様、弁財天など、特定の神仏の縁日がカレンダーで分かります。

「縁日」とは

◇「縁日」とは、特定の神仏と繋がり・ご縁が深くなる日です
「縁日(えんにち)」とは、特定の神仏と特別に繋がり、ご縁が深くなる日として、観音様や不動明用様など、それぞれ特定の神仏に割り当てられた日にちとなります。
仏菩薩様が「三十日秘仏」や神様が「三十番神」で割り当てられました。
また暦には十二支があり、縁日が十二支の暦で割り振られた神仏もいます。
| <縁日とは:3つの暦> | |
| [神仏] | [暦の種類] |
| ①神様 | ・十二支 |
| ②仏菩薩様 | ・三十日秘仏 |
| ③神様 | ・三十番神 |
もともとは西暦900年代の中国から始まったもので、例えばお不動様やお地蔵様、観音様など、特定の神様仏様に信心している人は、毎月の縁日に参拝をする人もありました。
特定の神様仏様に信心している場合、例えば18日が縁日の観音菩薩様を信心している人ならば、下一桁の8日にもお参りをする人もいます。
縁日とお祭りは違うの?
◇お祭りは、地域行事や祈願事が多いです
現代は縁日も「お祭り」のイメージが定着していますが、実は縁日とお祭りは違います。
お祭りは地域行事の色合いが強く、豊作・豊漁祈願などを行うために、海岸や畑、地域の集会所など、寺院仏閣以外の場所でも開催されるのが特徴です。
縁日には特定の神仏とのご縁を深めるため、その神仏を祀る神社寺院を訪れる、参拝客が大勢訪れますよね。
このような参拝客を目的として神社寺院周辺に市が立ち、いつしか縁日にお祭りのイメージが付きました。
例えば浅草寺では、年末12月17日~19日にお正月飾りが並ぶ「羽子板市(歳の市)」が行われますが、本来は浅草寺のご本尊「浅草観音(聖観音菩薩)」の縁日(18日)です。
納め拝みと初詣の違いとは?

年末と年始の参拝の位置づけ
現代では新年の「初詣」が一般的ですが、かつては年末の「納め拝み」で感謝を伝えることが重視されていました。
納め拝みは、その一年にお世話になった神仏へ「ありがとうございました」と感謝を捧げる行事です。
一方、初詣は新しい一年を迎えて「どうぞよろしくお願いします」と祈願するものです。
つまり、納め拝みは一年を締めくくる感謝、初詣は新年の祈願というように、役割が異なります。
縁日①十二支

◇干支日に割り当てられた縁日です
暦には、十二支が繰り返し訪れる「干支日(えとび)」があります。
干支日により割り当てられる縁日が、十二支による縁日です。
| <十二支による縁日> | |
| [十二支] | [神様] |
| ①寅(とら) | …毘沙門天 |
| ②巳(み) | …弁財天 |
| ③申(庚申)(さる) | …希釈天 |
| ④午(うま) | …稲荷明神 |
| ⑤亥(い) | …摩利支天 |
| ⑥子(甲子)(ね) | …大黒天 |
神棚や床の間に、安定した家計や家の繁栄を祈願して、大黒天様や弁財天様を祀る地域もあります。
このような家では干支日の縁日に、神棚や床の間の神様へ、お赤飯など特別なお供え物をして、拝む習慣もあるでしょう。
旧暦カレンダーなどの暦を見て上記の干支が入った暦が、それぞれの神様との縁日ですので注意をしてください。
縁日②三十秘仏

◇1か月30日に、それぞれの仏菩薩様を割り当てた縁日です
大阪では観音様(観音菩薩様)の縁日18日、お不動様(不動明王様)の縁日28日が比較的馴染み深いですが、観音様やお不動様の縁日も三十秘仏によるものです。
| <三十日秘仏による縁日> | |
| [縁日] | [仏菩薩様] |
| ・1日 | …妙見菩薩(みょうけんぼさつ) |
| ・5日 | …弥勒菩薩(みろくぼさつ)/水天宮 |
| ・7日 | …千手観音(せんじゅかんのん) |
| ・8日 | …薬師如来(やくしにょらい)/八幡宮 |
| ・13日 | …虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ) |
| ・14日 | …普賢菩薩(ふげんぼさつ) |
| ・15日 | …阿弥陀如来(あみだにょらい) |
| ・16日 | …閻魔王(えんまおう) |
| ・17日 | …龍樹菩薩(りゅうじゅぼさつ) |
| ・18日 | …観音菩薩(かんのんぼさつ) |
| ・23日 | …大勢至菩薩(だいせいしぼさつ) |
| ・24日 | …地蔵菩薩(じぞうぼさつ) |
| ・25日 | …文殊菩薩(もんじゅぼさつ) |
| ・27日 | …毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ) |
| ・28日 | …大日如来(だいにちにょらい) …不動明王(ふどうみょうおう) |
| ・30日 | …釈迦如来(しゃかにょらい) |
…縁日として割り当てられる「三十日秘仏」では、30日全ての暦に仏様が割り当てられていますが、より参拝客が多い縁日は上記の仏様でしょう。
また28日に大日如来、不動明王とともに並ぶ「三宝荒神(さんぽうこうじん)」様は火を司る台所の神様です。
地域によっては台所に三宝荒神を祀っていることもあり、このような時には家庭で拝みが行われることもあります。
縁日③三十番神

◇国守りのために30日交代で割り当てられた神様が「三十番神」です
縁日には法華経により国守りを司るため、30日の番神として割り当てられた神様が「三十番神(さんじゅうばんしん)」です
縁日でも三十番神の始まりは最澄による法華経・潅頂経ですので、三十番神に信心深い人々は主に日蓮宗の宗派が多いでしょう。
30日それぞれに割り当てられた番神は、鎌倉時代頃を起源とする天皇家の守護神などです。(禁闕守護三十番神)
| <縁日とは:三十番神> | |
| [縁日] | [神様] |
| ・1日 | …熱田大明神(あつただいみょうじん) |
| ・6日 | …鹿島大明神(かしまだいみょうじん) |
| ・10日 | …天照皇太神(あまてらすおおみかみ) |
| ・11日 | …八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ) |
| ・14日 | …大原大明神(おおはらだいみょうじん) |
| ・15日 | …春日大明神(かすがだいみょうじん) |
| ・17日 | …大比叡権現(おおひえいごんげん) |
| ・18日 | …小比叡権現(こひえいごんげん) |
| ・22日 | …稲荷大明神(いなりだいみょうじん) |
| ・23日 | …住吉大明神(すみよしだいみょうじん) |
| ・24日 | …祇園大明神(ぎおんだいみょうじん) |
| ・30日 | …吉備大明神(きびだいみょうじん) |
地域によっても違いがありますが、三十番神のなかでも大阪で広く知られる縁日は、上記のものなどが多いのではないでしょうか。
三十番神には仏教系(如法経守護三十番神/法華経守護三十番神など)と神道系(天地擁護三十番神/吾国守護三十番神など)がありますが、現代では稲荷大明神や住吉大明神など、特定の縁日に参拝するほどです。
師走の縁日に参拝する「納め拝み」とは?

◇一年を締めくくる12月の縁日に参拝して、一年の感謝を伝えます
現代は初詣文化が根付いていますが、かつては年末に拝む「納め拝み」が巡る新年を良い年にするために重要な行事でした。
「納め拝み」では、その年に参拝・祈願してお世話になった神仏へ、一年の締めくくりとなる年末に、感謝を捧げます。
| <縁日の納め拝み> | |
| [日付] | [納め拝み] |
| ・2025年12月5日(金) | …納め水天宮 |
| ・2025年12月8日(月) | …納め薬師如来 |
| ・2025年12月13日(土) | …納め虚空蔵菩薩 |
| ・2025年12月15日(月) | …納め阿弥陀如来 |
| ・2025年12月18日(木) | …納め観音 |
| ・2025年12月21日(日) | …納め大師 |
| ・2025年12月24日(水) | …納め地蔵菩薩 |
| ・2025年12月25日(木) | …終い天神 |
| ・2025年12月28日(日) | …納め不動 |
| ・2025年12月28日(日) | …納め大日如来 |
| ・2025年12月30日(火) | …納め釈迦如来 |
かつては集落の神様仏様を守護神として、日々お参りをしてきました。
そのため集落の神社がお祀りする神仏の縁日に、「今年もありがとうございました」と、年末の挨拶に伺う感覚だったのではないでしょうか。
「歳の市」は納め拝みの帰り
◇お正月飾りが並ぶ「羽子板市」や「歳の市」は、納め拝みの帰りです
現代では12月、師走の納め拝みの暦に合わせて、お正月飾りが並ぶ市「歳の市」や「羽子板市」で賑わいます。
| <2025年羽子板市(歳の市)> | |
| ①浅草寺 | |
| [日時] | 例年12月17日~19日(納め観音) |
| [場所] | 浅草寺 |
| [TEL] | 03(3842)0181 |
| [HP] | https://www.asakusa-toshinoichi.com/ |
| ②薬研掘不動院 | |
| [日時] | 例年12月26日~28日(納め不動) |
| [場所] | 薬研掘不動院 |
| [TEL] | 03(3866)3706 |
| [HP] | https://www.yagenborihudoin.com/ |
| ③おかげ横丁 | |
| [日時] | 例年12上旬 |
| [場所] | 三重県伊勢神宮:おかげ横丁 |
| [TEL] | 0596(23)8838 |
| [HP] | https://www.yagenborihudoin.com/ |
大阪市内では「納めの観音」などでの納め拝みを目安に、毎年12月17日頃、お正月用品を買い揃える家庭が多いでしょう。
大阪で熊手などの縁起物は、年明け1月9日~11日に掛けて行われる「えべっさん」十日戎で揃える人が多いです。
縁日や納め拝みに関するよくある質問(FAQ)

縁日や納め拝みについては、多くの人が同じような疑問を持ちます。ここでは、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
縁日は必ず参拝しないといけないの?
縁日は「必ず参拝しなければならない日」ではありません。
自分のご縁のある神仏に、節目の日として感謝を伝える機会と考えると良いでしょう。行けるときに無理なく参拝するのが一番です。
納め拝みは家でもできる?
はい。神社やお寺に足を運べない場合でも、ご家庭のお仏壇や神棚で一年の感謝をお祈りすることが、立派な納め拝みになります。
静かに手を合わせ、日々の平穏への感謝を伝えるだけでも十分です。
まとめ:年末の縁日に「納め拝み」を行うと福が巡ります

年末の「納めの観音」「納めの水天宮」など、一年の感謝を縁日に捧げる「納め拝み」を行う人々は少なくなりましたが、来年の福徳をもたらすと信じられてきました。
全国的には「初詣」が主流、お正月明けの参拝が根付いていますが、年末・年始の両方とも、縁日に参拝する人々もいます。
年始は縁日を目安にすることで、参拝客による混雑を避けることもできるでしょう。
・【2026年1月の年中行事カレンダー】正月飾りはいつしまう?十日戎の日程、初観音?
お電話でも受け付けております















